
着物を通して北海道の魅力を発信する、悉皆屋5代目の挑戦
8人介せば世界はつながる
フリーライターとして伝統芸能、美術工芸、医療、教育、料理、暮らし、演劇、就職、結婚、ファッションなど、多岐にわたるジャンルで取材、執筆活動をしている湊屋 一子さんによる連載企画「8人介せば世界はつながる」。
4半世紀を超えるキャリアの中で、最年少は10歳・最年長は95歳、のべ3000人以上にインタビューをしてきた湊屋さんが、今気になる人に会って話を聞き、ジャンルをまたいでつなげていきます。
父の実家は田舎の料理屋で、父の長兄である伯父が後を継いでいる。男ばかり5人の兄弟で、伯父以外は奨学金をもらうなどして大学を出ており、教育熱心な家庭だったことがうかがえるが、料理屋を継ぐと決まっていた伯父は高校を出てすぐ料理の修行に出たそうだ。昭和30年代なので、誰も何の疑問も持たなかったのだろう。家業を継ぐのは長男であり、むろん誰も継がないなどありえないと。
料理屋はともかく、世の中にはだんだんニーズが減って商売が先細っていく業種もある。そうした家業の家に生まれた子はどうなのだろう。職業選択の自由は無論保証されているが、いまだに「家業を継ぐ、継がない」は彼らにとって軽い問題ではないのではなかろうか。

「まあ、いずれは継ぐだろう、とは思ってましたね、漠然と」
北海道・札幌で、着物の手入れを請け負う悉皆屋として、歴史を刻んできた野口染補。その5代目である野口繁太郎さんは、高校まで大好きなサッカーの練習に明け暮れながら、なるべく家業から逃げたいと思っていたという。
「着物のことはよく知らないし、それでも着物を着る人が少なくて仕事は減る一方だとはわかってましたから」
継ぐものだと思いながら、その将来に希望が持てない。野口さんはワーキングホリデーで行ったオーストラリアで、意外にも海外に出て初めて家業について真剣に考えることになる。
「オーストラリアで『日本から来た』って言うと、まあ寿司のことは聞かれるのは予想してたんですが、着物のことを聞かれることもけっこうあって。でも自分は着物にかかわる仕事をしている家に生まれたのに、何にも着物について話せない。それが恥ずかしくて情けなくなっちゃって……着物っていう、海外で知られているものにかかわる家業だったんだ、ってオーストラリアまで来て教えられたんです」
それでもまだ、すぐに家業に飛び込もうとは思えなかった。さらに一か月でアメリカを横断するツアーに参加した。
「現地集合現地解散みたいな、いろんな国の人が出たり入ったりするツアーで、いろんなバックボーンを持つ人たちと話ができてすごく面白かったです。このツアーで身に染みてわかったのは『自分が発信しないと人に理解されない』ってことと、文化や歴史の違いを超えて、お互いの良さを理解しあう、それが人と出会う面白さとか豊かさなんだってことでした」
日本において着物を着る人は少数派、だから家業である悉皆の仕事は激減していくだろう。そう思っていた野口さんは「海外でも着物について知りたいと思っている人がいる。日本でも着物の魅力を知らない人が多いから、着物を着る人が少ない。自分もそうだった。なら、着物の魅力を自分で発信して、着物の魅力を知ってもらえれば、着る人を増やすことができるはず」と、巡り巡って着物の手入れではなく、着物そのものを作って広めることで、家業を継いでいこうと決意したのだ。
野口さんが着物を広めるために考えた条件は「自分で洗える」「強度が大切」といった、洋服の普段着だったら当然満たしているもの。まず手掛けたのはデニム素材の着物だった。

「私がデニムで着物を作ろうと思ったのは、近所にあるラグジュアリーブランドやビンテージのデニムの裾上げを専門にしている会社とのお付き合いの中で、貴重なビンテージデニムにたくさん触れる機会があり、着古されることで価値が上がる、使うことで価値が出る服っていいなと思ったのがきっかけです。デニムは誰もが日常的に着ていますし、手入れも楽で強度もある。こういう生地で着物を作ったら、いつかビンテージデニムみたいになるんじゃないか?と考えました」
野口さんがデニム着物の生産に着手した2008年当時、すでに世の中にデニム着物を出しているメーカーはわずかながらあり、彼がデニム着物の先駆者というわけではない。しかし着物と言えば歴史ある京都、あるいは大消費地・東京からはるか遠い北海道で、着物を日常着にしようなどという野望(?)を抱き、まず何か作ってみようとする野口さんは、相当なチャレンジャーだ。
「デニム着物を作るにあたって、よそは作ってないか探しては見ましたが、今ほどデニム着物を作っているところが見当たらなかったし、北海道というか私の知る範囲ではデニム着物を作っているところはありませんでした。自分で着て強度を確かめるだけじゃなくて、札幌で活動していた『ゴミ拾い侍 一世一代組』さんというパフォーマー集団の人たちにも衣装提供して、ラフに使ってもらって使用感を確かめてもらいました」
着物は男女で形が違うが、サイズが違っても基本的な構造はすべて同じで、多少袖の長さを変えるなどのアレンジがあるくらいで、一定の形であることが着物を着物たらしめている。つまり、どの着物も基本構造は同じで、昔から決まった数の決まった形のパーツを生地からとって、同じ縫い方でまとめるのが、伝統的な着物の作り方なのだ。それがゆえにサイズ変更が容易に可能であり、野口さんの家業である悉皆屋では、着物をほどいて縫い直してサイズを変えることも、主な仕事の一つになっている。
「しかし私が作るデニム着物は悉皆屋の出る幕がないんです(笑)」
一般的な着物の素材として多く使われているのは絹。これは自宅で洗うのが難しいため、悉皆屋などプロの手にゆだねてクリーニングするが、デニム着物は家庭の洗濯機で洗える。伝統的な着物は手縫いで作られるがゆえに、ほどいてパーツに戻し、サイズを変更も可能だが、デニム着物はミシン縫いなのでほどくのは困難であり、仕立て変えるというニーズは見込んでいない。
「ほどいてみればわかりますが、私の作るデニム着物は、伝統的な着物とは構造が違うんです。完成形で着物の形をしているけれど、省かれているパーツがけっこうあります」
なぜそうしたのか?
「伝統的な着物と同じ作り方をすると、デニムでは文字通り重くなりすぎる。襟周りなど、着物では布が四重になるところもありますが、そんなにデニムを重ねたら、首が重くてしょうがないし、洗っても中まで乾かない。構造にこだわるより、着心地がいい、洗濯が楽な方が大事だと思い、思い切って構造を変えて、パタンナーさんにパターンを引いてもらって着物を作りました」
着物の魅力を発信して、着物を気軽に着る人が増えれば、悉皆屋の仕事も増える……はずだったのでは?
「自分で着物を買ってみたり、着付け教室に行ってみたりして、私が感じたのは『このままじゃ絶対に広まらない』ということでした。絹の着物は値段も高いし手入れも自分で出来ない。着付けも難しくて大変。わざわざそれをしなさい、では、ちょっと着てみたいって人は入って来ないでしょう。だったらもっと敷居を低くして、気軽に毎日でも着られるような、そういう着物でまず着る人を増やして、すそ野を広げる。すそ野が広がれば、段階を踏んで絹の着物に進んでいく人もその中から現れるはずですから」


さらに楽に着るために、着物の下着にも新しいアイテムを投入した。着物はその下に長襦袢という、着物と同じ形をした下着をもう一枚重ねて、襟もとから覗かせる。その簡易版で半襦袢という、着物の上半分だけのようなものもあるが、どちらもうまく着物の襟から襦袢の襟が見えるように固定しなければならず、着用には一本紐が必要になる。野口さんはこれを、首周りに着物のような形をした襟をつけたTシャツにした。


このTシャツ型の襦袢も、野口さんが作るより以前に世には出ている。野口さんの工夫はそこに北海道ならではの魅力を加えたことだ。
「アイヌ刺繍作家さんとのご縁があって、せっかく北海道から発信するんだから、北海道ならではのものをと思って、アイヌの人たちが使ってきた文様を、襟に刺繍してもらうことにしたんです」
日本全国に着物にかかわる伝統技術がある中で、北海道にはそれらしいものがない。全国の着物生産者と対等に伍していくためにも、北海道ならではの着物文化を作りたかった。
「発売当初はまだマンガ『ゴールデンカムイ』ブームが来てなくて(笑)、一目でアイヌ文様とわかる人は少なかった。でもとにかくかっこいいとか不思議な柄だとか、そういうことで目に留まって、多くの人が着てくれるようになりました。今は襦袢Tシャツに加えて、刺繍だけでなく型染めや注染(※染物の技法)でアイヌ文様を表現した布を監修していただき、それで浴衣を作り、さらに浴衣を仕立てた時の残布を使ってワークパンツも作るようになりました。今後は織りでアイヌ文様を表現する布づくりにも挑戦して、もっとアイテムを増やしていきたいと考えています」

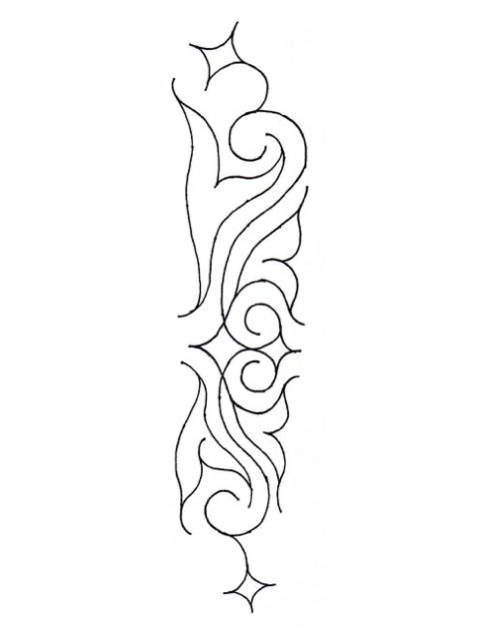
さらに北海道ならではの発信を考える野口さんが、今、手掛けているのは染物だ。コロナ禍の自粛期間に大きな打撃をこうむった業種の一つが飲食業だが、札幌は喫茶店の多い町でそうした喫茶店も例外ではなかった。 「私の仕事も大幅に減少した状態で、じゃあ何か他にやれることはないか?と思ってたんです。喫茶店文化も札幌の魅力の一つ。旅行に来てもらうことは難しい時期だけれど、札幌の町の魅力を広める方法はないか?と考えて、コーヒーを淹れた後に出るコーヒーの出涸らしを使った染物を思いつきました」


もともと家業がら染物はお手の物……かとおもいきや、草木染はまた別のものであり、野口さんは図書館に通って勉強し、試行錯誤をしながら、ただ捨てるばかりだったコーヒーの出涸らしを使った染物で街の文化を発信することに。徐々に自粛が解けてくると、子どもたちや観光客が参加できる染物ワークショップなども積極的に開催した。

「札幌の文化を取り入れたコーヒー染めをきっかけに、もっと染め物で北海道の魅力を発信できるものはないかと思うようになりました。そんな時、白樺に気づいたんです」
あまりに日常的に目にしすぎていて、気にも留めていなかった白樺。その白樺の樹液を使った製品を製造販売する会社が、原材料である白樺のために、北海道の山を育てていることを知った。
「山を育てるには適度な伐採が不可欠で、間伐材が出る。それを使って生地染めをやってみようと思いつきました。木を使った染物は、例えば奄美大島の大島紬が車輪梅を使っているように、着物に取り入れるのはありだなと。現地のものを使って現地で作る意味を感じさせる着物を発信して、北海道の染め物文化も作っていきたいと考えるようになりました」
何かをやろうと思ってから、実際にやるまでのスピードが速い野口さん。日常的に自分が着られる着物を作り、自ら発信することで着物ユーザーを増やして、そこから家業の振興につなげていこうというのもかなりな野望だったが、今や北海道の着物文化を作りたい!というところまで、野望のスケールは大きくなっている。しかし野口さんにはあまり気負いがない。
「結局、面白いことがしたいってことなんですよ。それでかかわってくれる人たちが喜んでくれて、お互いに仕事が増えるといいなって。たぶん考えてるのはそんなことですね」

野口繁太郎
野口染舗5代目。
創業1948年、着物の仕立て、クリーニング、シミ抜きや染め直しといった修繕などを手掛けている悉皆屋(しっかいや)。
2006年に野口染舗(のぐちせんぽ)へ入社。
「日本人と着物の間に出来てしまった距離を縮める」ことをブランドコンセプトにしたカジュアル キモノブランドShi bun no San(四分ノ三)を立ち上げる。
その中のアイテム「JUBAN Tシャツ®︎」は【おもてなしセレクション2016】を受賞しShi bun no Sanの必須アイテムになる。
北海道のキモノメーカーでは初であろう伊勢丹新宿本店でのPOPUPを皮切りに関東・中部・関西へと展開を広めていく。
モノを大切にする文化を次の世代へ伝える取り組みとして、染めの技術を活かし「洋服の染め替え」をはじめ、ハンカチやふろしきなどを自分で染める【染物体験】なども行っており、子供から大人、海外の方まで幅広い年代の方々にモノづくりの楽しさを伝えている。
また、新たなる取り組みとして北海道の文化や土地ならではの染色、モノづくりを発信するNOGUCHI SENPO Re COLOR PROJECTを企画。
※現在リブランディングしています。








